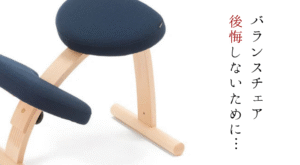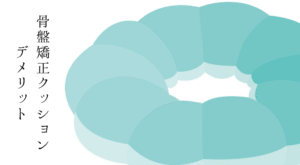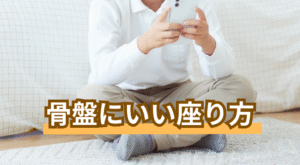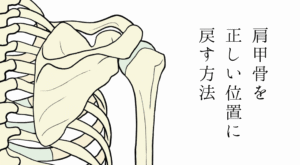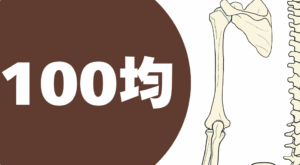床に座る生活と、椅子に座る生活。どっちが体にとってよいのか?
結論からお伝えしますね。
「椅子生活」です。だれが何と言おうと椅子生活です。
同じような題材を扱っているページもありますが、なかには「どっちもよい」みたいな結論づけている内容を目にすることがあります。それでも、15年以上、腰痛・肩痛などの不調に対する施術に携わってきた整骨院としての見解は断然「椅子生活」がおすすめです。
では、なぜ椅子生活のほうが体にとっておすすめだと言うのか。その答えも交えながら床生活と椅子生活について深堀りしていこうと思います。
長年の不調が改善しない人は、もしかすると座り方に原因があるのかもしれませんよ。
よろしければ最後までご覧ください。
床に座るよりも椅子に座るほうがおすすめの理由

15年以上整骨院を経営する柔道整復師のわたしが、床に座るよりも椅子に座るほうがおすすめだと結論付けるには理由があります。少し専門家らしく解説していきますが、なるべくかみ砕いて説明していきますね。
床座りは腰椎に負担を掛けやすい
床座りって腰椎(腰の骨)に負担を掛けやすいんです。
腰椎の形ってご存知ですか?腰痛は、イラストのように前カーブ(前弯)する形をとることで、全身のバランスを保っています。これを専門的には生理的弯曲と呼びます。
座るときも、この生理的弯曲を保った状態が理想とされています。腰椎で言えば前カーブを保つ状態が理想ということです。
| 座位 | LL(平均±SD) | 特徴 |
|---|---|---|
| 立位 | 47.1°±10.5° | 基準値 |
| 椅子(腰部サポート付) | 36.2°±8.4° | 前弯減少量 最小 |
| 90°-椅子 | 17.7°±4.4° | 前弯減少 中程度 |
| 椅子(前支持) | −4.9°±3.3° | 腰部後彎(Kyphosis) |
| スツール | 0.6°±3.6° | 腰部後彎 |
| 床座(あぐら/正座) | −7.4°±3.5° | 腰部後彎 最大 |
(1)
この表は座り方による腰椎の形をあらわしたものです。少し難しい表ですが、座位の部分をご覧ください。
特徴の部分を見ると、腰部後彎最大と書かれています。これは、座っているときに腰椎に後彎の力が働いていることを指します。
先述したように、腰椎は前弯(前カーブ)が最も負担の掛からない生理弯曲です。この前カーブに後ろカーブの力が働くということは腰椎にとって大きな負担になります。
一方、椅子座りを見ると、わずかに前弯が減少していますが、床座りのように大きな後彎の力は働いていません。
このデータからわかるように、床座りは体(特に腰)へ大きな負担を掛けることから、椅子座りをおすすめしています。
梨状筋に負担を掛ける
床座り(あぐら)は、梨状筋と呼ばれるお尻の筋肉に過度な伸長を加え、骨盤の仙腸関節を不安定にさせるという報告もあります。(2)
梨状筋に負担が掛かり、ストレスになると坐骨神経痛を発症させる梨状筋症候群になりやすく、お尻や太ももへの痛みやしびれを伴います。
本報告では、あぐらのみの座り方に言及していましたが、女性特有のお姉さん座りをしている方にも坐骨神経痛の症状が多い印象が、あくまでもわたしの経験値だけですがあります。
厚生労働省も注意喚起をしている
床座りを避けるよう言っているのは、厚生労働省も同じです。
職場における腰痛予防対策指針では、「直接床に座る座作業は、仙腸関節、股関節等に負担がかかるため、できる限り避けるよう配慮すること」(3)としており、床座りに対して警告を促しています。
このように、個人の見解ではなく幅広いデーターや公的機関の通告からみても、床座りは避けるべきであり、椅子座りのほうがおすすめだと結論付けられているのです。
実際にあった「床座り」が原因と思われる不調

整骨院での施術経験から、床座りが原因と考えられる不調事例をご紹介します。これらは決して珍しいケースではなく、床座り中心の生活を送る方によく見られる症状です。
腰痛が慢性化した50代男性
テレビを見るさいに、常にあぐらをかく生活を20年以上続けていた男性患者さんのケースです。
初見時には腰を反らすことができず、前屈姿勢が固定化していました。整形外科でのレントゲン検査では腰椎の自然なカーブが失われ、椎間板の狭さを指摘されたそうです。
この方の場合、長年のあぐら姿勢により骨盤が後傾し、腰椎への圧迫が慢性化していました。施術と並行して椅子生活をすすめたところ、3か月後には腰痛の痛み・頻度ともに大幅な減少を確認できました。

膝が曲がらなくなった60代女性
茶道を長年続けてきた女性患者さんで、正座中心の生活により膝関節の拘縮が進行したケースです。
階段の昇降時に膝が十分に曲がらず、日常生活に支障をきたしていました。正座により関節可動域が制限されていました。半年以上の継続施術により改善はみられましたが、正座習慣の見直しが根本的な解決策となりました。
現在は椅子での茶道スタイルに変更し、膝の調子も安定しています。
猫背と巻き肩に悩む40代女性
床に座ってスマートフォンを使用することが多い女性患者さんのケースです。
首が前方に突き出し、肩が内側に巻き込まれた姿勢が固定化していました。頭痛や肩こりに加え、呼吸の浅さも訴えていました。
床座り+スマートフォン使用により、首や肩への負担が限界に達していました。椅子とデスクを使用した環境に変更し、姿勢改善のエクササイズを継続したところ、3か月後には見た目の変化も明らかになりました。

正しい椅子の座り方

本ページでは、床座りではなく椅子座りをおすすめしていますが、椅子に座れば万事解決ではありません。当然ながら、正しい椅子の座り方があります。以下では、その方法をご紹介します。
椅子&周囲の環境を整える
正しい椅子座りでは、座面の高さ調整が大切です。
膝が90度になる高さで、足裏全体が床につくように設定します。足がつかない場合は足置き(フットレスト)を使用しましょう。太ももと座面の間に、手のひら1枚分程度の隙間があるのが理想的です。
背もたれには軽くもたれかかり、腰を反らせすぎないよう注意します。腰椎の自然なカーブを保つために、背もたれの角度は100~110度程度が適切です。肩の力を抜き、肘は90度で机に軽く置ける高さに調整します。
パソコン作業時は画面の上端が目線の高さになるよう調整し、首を前に突き出さないよう心がけましょう。(4)
骨盤を立てて座る正しい方法
椅子座りで最も重要なのは「骨盤を立てて座る」ことです。
骨盤を立てるとは、骨盤が前にも後ろにも傾かず、垂直に近い状態を保つことを指します。
まず、お尻を後ろに突き出すように椅子に深く腰掛けます(スクワットのフォームのように)。このとき、お尻の下にある坐骨(座った時に椅子に当たる骨)を意識します。この坐骨で椅子の座面をしっかりと捉えるイメージで座りましょう。次に、軽く胸を張り、頭頂部を天井に向けて引き上げるよに座ります。
この時、腰を反らせすぎないよう注意が必要です。「気をつけ」の姿勢のように背中をピンと張るのではなく、自然な背骨のカーブを保ちながら、骨盤を起こすことがポイントです。正しく座れると、腰への負担が軽減され、長時間座っても疲れにくくなります。
正しく座れているかの確認は、脚を組もうとしてみてください。正しく座れていると、脚を組みたくても組めません。
正しい床の座り方
正直なところ、100%正しい床の座り方はありません。
実際、わたしの整骨院では多くの方に椅子座りへの生活様式の変更をお願いしています。生活様式を変えることは簡単ではないことを承知しています。それでも、不調の原因となるものは排除すべきです。大変でも行動に移すか移さないかで状況は大きく変わっていきます。
それでも、床座りの生活しかできない方には、正しい座り方はご提案できませんが、避けるべき座り方であれば以下のようにご提案できます。
- 体育座り
- 横座り(お姉さん座り)
- アヒル座り
- あぐら(両足裏くっ付けるならOK)
以上の床座りは、坐骨・股関節・膝関節に負担の掛けやすい座り方であるため避けましょう。
となると、長座・あぐらなどの座り方しかなくなりますが、これらの座り方も長時間は避けて定期的に立ち上がるなどの対策が必要です。
まとめ
長年の臨床経験から断言できるのは、体への負担が少ないのは圧倒的に椅子生活だということです。
床生活は日本の文化として親しまれてきましたが、現代人の体力や生活スタイルを考慮すると、健康面でのリスクが高いのが現実です。
特に腰・股関節・膝に不安がある方、長時間座る必要がある方には、椅子生活が圧倒的におすすめです。慢性的な不調に悩まされている方は、まず座る環境を見直すことから始めてみてください。
座る時間が長い現代だからこそ、「どう座るか」が健康維持のカギとなります。床座りから椅子座りへの移行は、単なる生活スタイルの変更ではなく、将来の健康への投資と考えていただければ幸いです。