折りたたみマットレスの購入を検討している
折りたたみマットレスって腰痛になりやすいって本当?
コンパクトだから購入したいけど健康面が気になる…
コンパクトに折りたためる利便性が人気の折りたたみマットレス。多くの方が購入を検討されている最中に本ページへたどり着かれたのではないでしょうか。
筆者は、15年間整骨院を経営しており、これまで多くの方の体の不調に携わってきました。そんな筆者の経験から申し上げさせていただくと、折りたたみマットレスが腰痛になりやすいというのは本当です。
しかし、対策もあります。
本ページでは、折りたたみマットレスのデメリットについて専門家の目線からお伝えさせていただくと同時に、折りたたみマットレスを健康的に使用する対策についてもお伝えさせていただきます。
これから折りたたみマットレスを購入しようかと検討されている方は、ぜひ最後までご覧ください。
折りたたみマットレス「5つ」のデメリット

収納性が最大のメリットである折りたたみマットレスですが、購入前に知っておいて欲しい5つのデメリットがあります。このデメリットを知らずに折りたたみマットレスを購入すると後悔するリスクが高まってしまうためご注意ください。
腰痛の原因になる可能性がある
折りたたみマットレスの多くは、通常の一枚ものマットレスと比較して厚みや反発力が不足しがちです。
そのため身体の重い部分(腰・お尻回り)が沈み込みやすく、理想的な寝姿勢を保つことが難しくなります。これにより脊椎のS字カーブが崩れ、腰に負担がかかりやすい状態になってしまいます。
特に反り腰の方は腰部の負担が増大し、腰痛をさらに悪化させてしまう可能性もあるでしょう。また、猫背の方も肩甲骨周りの筋肉が緊張したまま眠ることになり、肩こりや頭痛を発症しやすくなります。
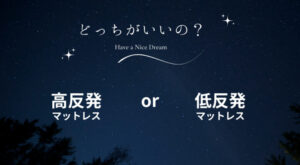
体圧分散が不十分な商品が多い
折りたたみマットレスでは、体圧分散性が不十分な商品が多い点がデメリットのひとつです。
良質な睡眠には、体圧が均等に分散されることが重要ですが、折りたたみマットレスではこの機能が不足している点がデメリットとしてあげられます。
折りたたみマットレスで体圧分散性が不十分になる最大の理由は「折り目」が存在することです。
折りたたみマットレスは、その名前のとおり折りたたみができるマットレスのため、マットレスの数カ所に折り目が存在します。この部分が脆弱になってしまうため、一枚ものマットレスと比較すると体圧分散性が劣りがちです。
もちろん、高品質の折りたたみマットレスでは、このデメリットを最大限にカバーした商品も存在しますが、それでも一枚ものマットレスと比較した場合には劣ってしまうのが現状です。
ヘタりやすく長持ちしにくい
折りたたみマットレスは、ヘタりやすく長持ちしにくい点もデメリットです。
折りたたみマットレスの多くはウレタン素材を使用していますが、このウレタンは経年劣化しやすいという欠点があります。特に、折りたたむ部分は繰り返しの負荷がかかるため、他の部分よりも早くヘタってしまいます。
一般的な折りたたみマットレスの耐用年数は約2〜3年程度と言われており、毎日使用する場合はさらに短くなる可能性があります。
ヘタってくると徐々に体を支える力が弱まり、寝返りがしづらくなったり、腰への負担が増えたりします。コストパフォーマンスを考えると、長期的には割高になることもあるでしょう。
通気性が悪くカビやすい
折りたたみマットレスは構造上、通気性が一般的な一枚ものマットレスより劣る傾向があります。
特に、三つ折りタイプは折り目部分に湿気がこもりやすく、カビの発生リスクが高まります。敷きっぱなしで使用していると、マットレスの下部に湿気が溜まり、知らない間にカビが発生していることも少なくありません。
カビはアレルギー症状や呼吸器系の問題を引き起こす可能性があり、健康面でのリスクとなります。
また、定期的に干す必要がありますが、重さや大きさから手入れが面倒で、結果的にメンテナンスが疎かになる方も多いです。
折り目の段差で寝心地が悪くなることも
折りたたみマットレスの最大の特徴である「折り目」が最大のデメリットとなることがあります。
特に、使用期間が長くなると、折り目部分に段差が生じてきます。この段差が身体のちょうど腰や肩の下に来ると、不自然な姿勢で眠ることになり、筋肉への負担が増加します。
また、折り目部分は他の部分よりも早く沈み込む傾向があるため、体のラインに沿った自然な寝姿勢を保つことが難しくなります。これにより寝返りの回数が増え、睡眠の質が低下する可能性があるのです。
折りたたみマットレスを選ぶときに注意すべきポイント

折りたたみマットレスのデメリットをご確認いただいたうえで「折りたたみマットレスが欲しい!」とお考えの方へ購入時の注意点をお伝えさせていただきます。
厚さ・硬さ・素材を確認する
折りたたみマットレスを選ぶときは、まず厚さを重視しましょう。体重の重い方や側臥位(横向き)で寝る方は、最低でも8cm以上、できれば10cm以上の厚みがあるものがおすすめです。
硬さについては、体重や好みによって異なりますが、柔らかすぎると体が沈みこみすぎて腰への負担が増加するため高反発素材をおすすめします。
素材は耐久性と通気性に優れたものを選びましょう。高密度ウレタンフォームや、上層部にジェル素材や低反発素材を組み合わせたハイブリッドタイプは体圧分散に優れています。
値段だけで選ばず、スペックをしっかり確認することが大切です。
三つ折りよりも「一枚もの」に近い構造を選ぶ
折りたたみマットレスを選ぶなら、なるべく折り目の少ないタイプがおすすめです。
三つ折りよりも二つ折りの方が折り目による段差の影響が少なく、より自然な寝姿勢を保ちやすくなります。また、最近では折り目部分の構造に工夫を凝らし、使用時にほぼ一枚ものと同じような平面を実現する商品も増えています。
折り目が体の中心に来ないよう、身長に合わせたサイズ選びも重要です。特に身長が高い方は、足元ではなく腰や背中の下に折り目が来ないよう注意しましょう。

トライアル制度を利用する
マットレスは実際に横になってみないと、自分の体に合うかどうかわかりません。可能であれば、展示品で試し寝をしてから購入することをおすすめします。試し寝の際は、普段の寝姿勢(仰向け・横向き・うつ伏せなど)で最低でも5分程度横になり、体が沈みすぎていないか、違和感がないかをチェックしましょう。
また、多くのメーカーでは返品保証やトライアル期間を設けていますので、それらのサービスを積極的に活用することをおすすめいます。
実際に数日間使用してみて、朝の目覚めや体の状態をチェックすることで、より確実に自分に合ったマットレスを見つけることができます。
折りたたみマットレスをおすすめできる人・できない人

本ページをご覧いただいて、折りたたみマットレスの購入を少し躊躇された方は、もう一度自分にとって折りたたみマットレスが必要なものかを検討してみましょう。
その判断材料のひとつとして、折りたたみマットレスをおすすめできる人とおすすめできない人の特徴をご紹介していきます。
おすすめできる人
折りたたみマットレスをおすすめできる人は、限られたスペースで生活している方です。一人暮らしのワンルームや学生寮など、日中はマットレスを片付けたい場合に非常に便利です。
また、頻繁に引っ越しする予定がある方や、持ち運びのしやすさを重視する方にもおすすめです。
体重が軽め(目安として60kg以下)の方や、仰向けで寝る習慣がある方も、適切な厚みと硬さの折りたたみマットレスであれば快適に使用できる可能性が高いです。
さらに、来客用の予備寝具として時々使用する場合にも適しています。予算を抑えて寝具を揃えたい方にもコスト面で魅力的な選択肢となります。

おすすめできない人
折りたたみマットレスをおすすめできない人は、慢性的な腰痛や肩こりに悩まされている方です。これらの症状がある場合は、より体圧分散性に優れた通常のマットレスや、体に合った硬さの敷布団をおすすめします。
また、睡眠の質を特に重視する方や、一日の疲れをしっかり取りたい方には物足りない可能性があります。
体重が重い方(目安として80kg以上)も、一般的な折りたたみマットレスでは十分なサポート力が得られないことが多いです。
毎日の使用で長期間(5年以上)使い続けたい方も、耐久性の面から通常のマットレスの方が結果的にコスパが良いケースが多いでしょう。

まとめ
折りたたみマットレスは収納性や価格の面で大きなメリットがありますが、腰痛予防や改善を考えると注意点も多いことがわかりました。
特に厚みや反発力が不足していると、体の重い部分が沈み込み、脊椎に負担がかかりやすくなります。
また、折り目の段差や通気性の問題、耐久性の短さなども考慮すべきポイントです。
しかし、適切な商品選びをすれば、折りたたみタイプでも快適に使用できる可能性はあります。マットレス選びは、体型や寝姿勢、体重、生活スタイルなど個人差が大きいため、可能な限り試し寝をしたり、返品保証のあるものを選んだりするのが賢明です。
腰痛でお悩みの方は、整骨院など専門家に相談してから購入を検討されることをおすすめします。健康的な睡眠のためには、便利さだけでなく体への影響も十分に考慮した寝具選びが重要です。








ご質問&ご相談